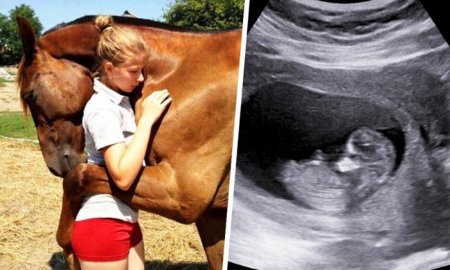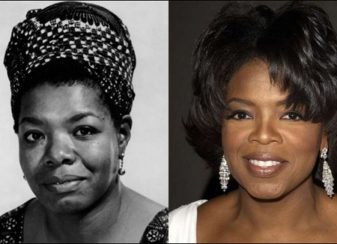はちみつには太る要素がある?痩せる効果やおすすめの食べ方を解説
食・料理

Advertisements
監修者:管理栄養士 児玉智絢(こだまちひろ)
はちみつは甘みが強いため、太る要因になると考えられがちだ。しかし、はちみつは食べ方を工夫すれば、逆にダイエットに役立たせることもできる。そこで、本記事では太るリスクを避ける上手なはちみつの食べ方を紹介する。
目次
- 1. はちみつに太る要素はあるのか
- 2. はちみつがダイエット向きな理由
- 3. はちみつの太る要素を避ける食べ方
1. はちみつに太る要素はあるのか

はちみつは砂糖のように甘味料として用いられる食品だ。カロリーや糖質量はどのくらいなのだろうか。栄養成分について見ていこう。
主な栄養成分
「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(※1)によると、はちみつのカロリーと主成分は下記の通りである。
- カロリー:100gあたり329kcal、大さじ1杯(21g)あたり69kcal
- 炭水化物(糖質):100gあたり81.7g、大さじ1杯(21g)あたり17.2g
はちみつは、ほとんどが炭水化物(糖質)でできている。カリウムが100gあたり65mg含まれるが、ほかのミネラル、ビタミン類、たんぱく質は微量だ。
一般的な上白糖(※2)のカロリー(100gあたり391kcal)と糖質量(100gあたり99.3g)に比べるとやや低いが、食べすぎるとカロリーの過剰摂取となり太るリスクが高まる。
カロリーや糖質はほかの食品からも摂取するため、はちみつの摂取量は一日あたり大さじ1~2杯(21~42g)程度までを目安にするとよいだろう。
2. はちみつがダイエット向きな理由

はちみつは糖質もカロリーも高いため、食べすぎると太る要因になる。しかし、甘味料として上手に使えば痩せる効果を得られる可能性もある。はちみつは天然の糖分では最も甘みが強いといわれ、砂糖の1/3程度の量で同等の甘みを出すことができる(※3)。そのため、砂糖の代わりに使用すれば、カロリーと糖質の摂取量を減らせるのだ。また、はちみつには下記のようなメリットもある。
GI値が低い
食後血糖値の上昇具合をあらわす指標をGI値といい、値が低い食品ほど血糖値が上がりにくい。ブドウ糖を100とした相対値で示され、70以上が高GI、55以下が低GIとされる。はちみつは種類にもよるが、低~中GI食品に分類されるものもある。「みつばち健康科学研究所」の資料によると、とくに国産のアカシアはちみつのGI値が低い。(※4、5)
はちみつのGI値が低いのは、主な糖質がブドウ糖ではなく果糖だからである。血中に吸収された果糖は血糖値を上げる要因にはならないが、摂りすぎると脂肪に変換される。GI値が低くても、やはり食べすぎないよう注意が必要だ。(※4)
Advertisements
整腸機能
はちみつには、オリゴ糖酸の一つであるマルトビオン酸が含まれている。難消化性のため腸内に到達し、ビフィズス菌のエサとなりビフィズス菌を増殖させる作用のある物質だ。そのため、はちみつを食べることにより整腸作用を促す効果も期待できる。(※6)
腸内環境を整えることは、ダイエットの大敵である便秘の予防や解消につなげられる。
3. はちみつの太る要素を避ける食べ方

はちみつを食べすぎるだけでなく、カロリーの高いものと組み合わせるのも太るリスクの高まる食べ方だ。カロリーや糖質を余分に摂らないためには、砂糖の代わり(甘味料)として使うことが望ましい。料理に使用するほか、下記のような食べ方で気軽に取り入れよう。
おすすめの食べ方
【はちみつヨーグルト】
無糖のヨーグルトにはちみつで甘みをつける。砂糖を加えるより使用量をおさえられ、整腸効果も期待できる(※3、6)。
【はちみつレモン】
さっぱりして食べやすく、レモンの栄養も摂取できる。そのまま食べるだけでなく、レモネードにアレンジもできる。
【紅茶やコーヒーに入れる】
砂糖の代わりにはちみつを入れることで、カロリーと糖質の摂取量が減り、血糖値の上昇も緩やかになる(※1~5)。
結論
はちみつは主に炭水化物(糖質)でできているため、カロリーも高めである。そのため、食べすぎると太る可能性は高い。しかし、砂糖(上白糖)と比較するとカロリーも糖質量も低い。さらに甘みが強いため、砂糖の代わりに使えば摂取カロリーをおさえることができる。また、低GI値食品で整腸作用があるという、太るリスクを下げる側面ももつ。食べすぎないように気を付けつつ、はちみつを食生活に取り入れてはいかがだろう。
(参考文献)
- ※1、2出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」https://fooddb.mext.go.jp/
- ※3出典:医療法人 豊隆会 ちくさ病院「ちくさ病院近藤先生が実践する民間療法」https://chikusa-zaitaku.jp/news/p16539/
- ※4出典:医療法人紘祥会 日置クリニック「血糖値を下げる食事術「果物・ハチミツは大丈夫」はウソ?」https://hiki-clinic.or.jp/column/health/lower-blood-sugar/
- ※5出典:株式会社山田養蜂場みつばち健康科学研究所「はちみつ 明らかになる健康機能~最新研究ダイジェスト」https://www.bee-lab.jp/megumi/honey/data.html
- ※6出典:公益社団法人 日本農芸化学会「化学と生物(Vol. 50, No. 12, 2012)」蜂蜜中に含まれるオリゴ糖酸『マルトビオン酸』(深見 健、サンエイ糖化(株)素材開発部)https://katosei.jsbba.or.jp/download_pdf.php?aid=50970